大宝八幡宮で頒布をしている御札・御守と、社宝、境内施設の一部をご紹介します。 御札・御守は、新年を迎えるにあたり新しいものをお受けいただくのが一般的です。これは、御札・御守を新しくすることにより、御神霊の力、御神威(みいつ)がさらに活発に発揚されると考えられているためです。伊勢の神宮をはじめ全国でみられる遷宮(せんぐう)(社殿を新築し神様に御遷りいただくこと)にも、このような意味合いが含まれています。 ※ここにご紹介しきれていない授与品・社宝・境内施設もございます。
141件の情報項目より86-90件を表示しております
茨城百景

重軽石

石自体は特別な物ではなく、実際には重さは変わりませんが、参拝の前と後とでは、重さが違って感じられる石です。参拝をして真剣に神様に感謝・祈願・報告などをした人は、晴れやかな気持ちになり体が軽く感じられるので、その状態で石を持ち上げると、参拝前より軽くなるのです。
とても嬉しい事があったり、悩みを聞いてもらったら肩の荷が下りたような気がしたり、仕事が終わって疲れていても「明日から3連休だ」と思うと急に元気が出たり、そんな精神状態に近いと考えるとわかりやすいでしょうか。
忠魂碑

大正十四年、帝國在郷軍人會 大寶村分會により建てられた碑。昭和三十年、大寶地區遺族會により改装されたものが現存しています。
さざれ石

さざれ石の学名は、石灰質角礫岩。全国各地の石灰質の山や谷で産出しますが、この石は国歌発祥の地といわれる岐阜県揖斐郡春日村の山中にあったものです。
下妻政泰公忠死之碑

下妻政泰公忠死之碑
大宝城最後の城主、下妻政泰公の碑。南北朝時代、南朝方に付いた政泰公は、大宝城を北朝の軍勢に包囲され、食料不足と城内不和により敗北。興國四年(康永二年)十一月十二日、政泰公は討死し、大宝城は落城しました。
大宝城最後の城主、下妻政泰公の碑。南北朝時代、南朝方に付いた政泰公は、大宝城を北朝の軍勢に包囲され、食料不足と城内不和により敗北。興國四年(康永二年)十一月十二日、政泰公は討死し、大宝城は落城しました。
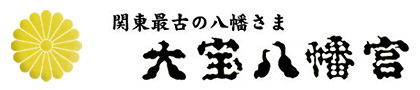
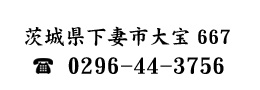

大宝駅を出て正面の坂(敵返坂)を登る途中、右手にあります。