大宝八幡宮で頒布をしている御札・御守と、社宝、境内施設の一部をご紹介します。 御札・御守は、新年を迎えるにあたり新しいものをお受けいただくのが一般的です。これは、御札・御守を新しくすることにより、御神霊の力、御神威(みいつ)がさらに活発に発揚されると考えられているためです。伊勢の神宮をはじめ全国でみられる遷宮(せんぐう)(社殿を新築し神様に御遷りいただくこと)にも、このような意味合いが含まれています。 ※ここにご紹介しきれていない授与品・社宝・境内施設もございます。
141件の情報項目より76-80件を表示しております
寶物殿(資料館)

社務所

社務所
御祈祷の受付、御札・御守の授与など、社務全般を行っている所。毎朝8時半から夕方5時まで神職が常駐しています。御祈祷の受付は曜日や祝祭日に関わらず朝9時から夕方4時半までですが、正月・祭事などによりこの限りではありません。現在の社務所は崇敬篤い井岡氏の奉納(昭和55年)であり、その偉業を称える記念碑が拝殿脇に建てられています。
御祈祷の受付、御札・御守の授与など、社務全般を行っている所。毎朝8時半から夕方5時まで神職が常駐しています。御祈祷の受付は曜日や祝祭日に関わらず朝9時から夕方4時半までですが、正月・祭事などによりこの限りではありません。現在の社務所は崇敬篤い井岡氏の奉納(昭和55年)であり、その偉業を称える記念碑が拝殿脇に建てられています。
神楽殿

神楽殿
神楽とは神を祀るときに奏上する舞と音楽。神楽殿とは神社の境内に設けて神楽を奏する殿舎をいいます。天照大御神が天の岩戸にお隠れになったとき、八百万の神々が岩戸の前に集まって踊りを舞い、天照大御神のお出ましを願ったという神話が起源といわれます。春と秋の例祭では十二座神楽が奉納され、例祭と節分祭では豆・餅・菓子などをここから撒きます。また、神事とは別にコンサートなどにも使われます。
神楽とは神を祀るときに奏上する舞と音楽。神楽殿とは神社の境内に設けて神楽を奏する殿舎をいいます。天照大御神が天の岩戸にお隠れになったとき、八百万の神々が岩戸の前に集まって踊りを舞い、天照大御神のお出ましを願ったという神話が起源といわれます。春と秋の例祭では十二座神楽が奉納され、例祭と節分祭では豆・餅・菓子などをここから撒きます。また、神事とは別にコンサートなどにも使われます。
手水舎

御神前に進む前に日常の生活の中から誰もが身に着けてしまっている「罪」や「穢れ」を祓い清める所。身体全体を水などで祓い清める「禊」が簡略化されたのが手水です。参拝の前に立ち寄り、必ず手水を行ってから御神前に進むのが神様への礼儀作法です。
青龍権現社

かつて大宝沼に住んでいたと伝説が残る
白い大蛇を祀ったお社。
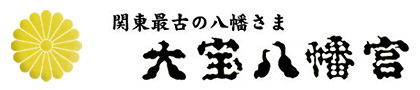
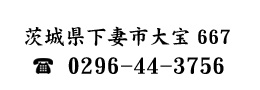

土器・戦国時代の具足・皇室御下賜品など数多くの宝物が納められています。代表的なものは、瑞花雙鳥八陵鏡・丸木舟・銅鐘(いずれも県指定文化財)の三点が挙げられます。拝観料は大人200円、小学生以下100円。