大宝八幡宮で頒布をしている御札・御守と、社宝、境内施設の一部をご紹介します。 御札・御守は、新年を迎えるにあたり新しいものをお受けいただくのが一般的です。これは、御札・御守を新しくすることにより、御神霊の力、御神威(みいつ)がさらに活発に発揚されると考えられているためです。伊勢の神宮をはじめ全国でみられる遷宮(せんぐう)(社殿を新築し神様に御遷りいただくこと)にも、このような意味合いが含まれています。 ※ここにご紹介しきれていない授与品・社宝・境内施設もございます。
141件の情報項目より41-45件を表示しております
瑞花雙鳥八陵鏡

丸木船

丸木船
県指定文化財。
イトスギ材、長さ6,05メートル、幅58センチメートル。
船首と船尾をとがらせている。江戸時代後期安政年間(1854〜1859年)に大宝沼干拓の際発見されたと言われる。
浅瀬で運搬用に使われていたものと考えられている。船底は平たんに近い造りで、舷の内外とも精巧に削られているのが特色になっている。大木の幹をくりぬいて造った丸木船はくりぶねともいわれる。見事な造りのこの丸木船は、古墳時代後期のものと考えられ、ほぼ完全な形で保存も極めて良好、貴重な考古学資料として高く評価されている。
県指定文化財。
イトスギ材、長さ6,05メートル、幅58センチメートル。
船首と船尾をとがらせている。江戸時代後期安政年間(1854〜1859年)に大宝沼干拓の際発見されたと言われる。
浅瀬で運搬用に使われていたものと考えられている。船底は平たんに近い造りで、舷の内外とも精巧に削られているのが特色になっている。大木の幹をくりぬいて造った丸木船はくりぶねともいわれる。見事な造りのこの丸木船は、古墳時代後期のものと考えられ、ほぼ完全な形で保存も極めて良好、貴重な考古学資料として高く評価されている。
銅鐘

銅鐘(どうしょう)
県指定文化財。
高さ108.1センチメートル、口径60.3センチメートル。
池の間(鐘の中間にあるほぼ方形の四区)の陰刻銘により、鐘は埼玉県岩槻市平林寺を開山した石室善玖が1387年(嘉慶一)鋳造。大工沙弥道善作とわかる。その後1456年(享徳5、康正2)猿島郡星智寺のものとなったことが三区以下の追名で知れる。
この鐘は1546年(天正1)9月、佐竹氏の先手となった多賀谷重経が、猿島郡へ出陣の際に戦利品として持ち帰り、大宝八幡宮に奉納したものと伝えられる。
県指定文化財。
高さ108.1センチメートル、口径60.3センチメートル。
池の間(鐘の中間にあるほぼ方形の四区)の陰刻銘により、鐘は埼玉県岩槻市平林寺を開山した石室善玖が1387年(嘉慶一)鋳造。大工沙弥道善作とわかる。その後1456年(享徳5、康正2)猿島郡星智寺のものとなったことが三区以下の追名で知れる。
この鐘は1546年(天正1)9月、佐竹氏の先手となった多賀谷重経が、猿島郡へ出陣の際に戦利品として持ち帰り、大宝八幡宮に奉納したものと伝えられる。
徳川家朱印状の桐箱

徳川家より社領115石が寄進され、
代々の朱印状が現存します。
※朱印状は桐箱に収められた状態で展示してあります
徳川家朱印状1

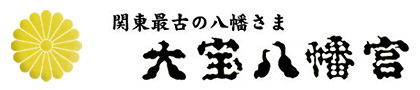
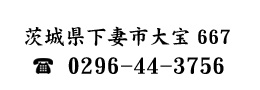

県指定文化財。
白銅製、11.2センチメートル。
文様表出のよい精良な一面である。鏡背文様は四分割して上下に瑞花を散らし、左右に鳳凰対称的に配し、さらに周囲には羽を広げた蝶を四方に対称的におき、そのあいだに唐草を散らしている。
鋳造年代は11世紀頃であろう。